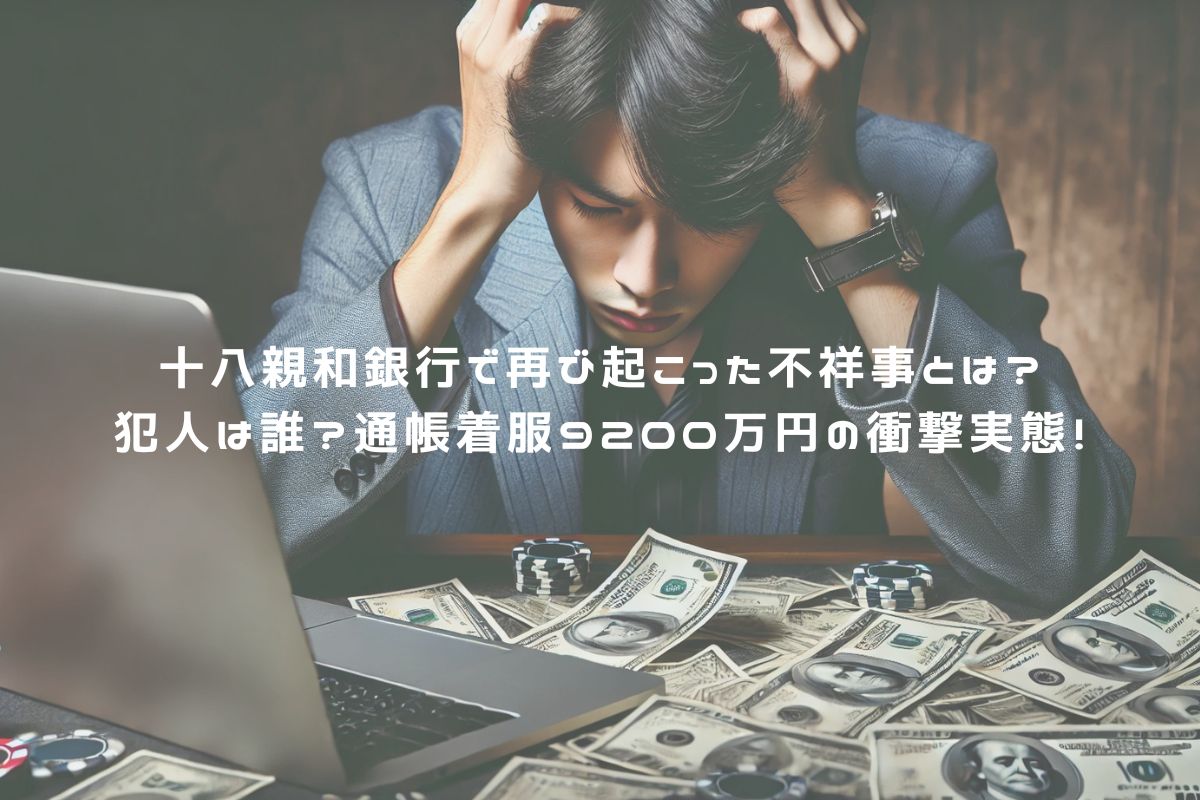金融機関としてあってはならない事件が世間を揺るがせています。
長崎を拠点とする十八親和銀行で、現役行員が約9200万円もの巨額を着服。
しかもその犯行は、4年以上にわたって一人の顧客から繰り返されていたという驚きの内容です。
「一体、犯人は誰なのか?」
「どうしてこんな不祥事が立て続けに起こるのか?」
この記事では、犯人の素性や動機、銀行の管理体制の問題点、再発防止策の甘さまで、徹底的に解説します。
この記事を読むことで、銀行に預けるお金の「本当の安全性」について、改めて考えるきっかけになるはずです。
不安を感じている方こそ、ぜひ最後まで目を通してみてくださいね。
\買い忘れはありませんか?/
十八親和銀行の不祥事の全容と犯人は誰

十八親和銀行の不祥事の全容と犯人の正体について詳しくお伝えします。
着服した金額とその手口
今回の事件で着服された金額は、約9,200万円にも上りました。
この金額は、行員であった32歳の男性が、顧客から預かった通帳を使って、無断で現金を引き出すという非常に悪質な方法によって得たものです。
この行員は、2020年6月から2024年10月までの約4年間、1人の高齢顧客をターゲットにして着服を繰り返していたとされています。
銀行の記録に残らないよう、ATMから少額ずつ何度も引き出すという手法も取り入れていたようです。
さらに、預金だけではなく、返済の見込みがないまま金を借りるという形でも資金をかき集めていました。
まさかこんなにも長期にわたり、一人の顧客から狙われ続けていたとは信じがたいですよね。
犯人のプロフィールと勤務歴
犯人は、長崎市に本店を構える十八親和銀行の本部に勤務していた32歳の男性行員です。
事件当時は、本部勤務でしたが、問題の始まりは支店勤務時代にまでさかのぼります。
当初は誠実で優しい印象を持たれていたとの声もありますが、裏では私的な借金やギャンブルに悩まされていた模様です。
被害者となった高齢の顧客とは長年の信頼関係があり、そこにつけ込んで複数の通帳を預かり、さらには暗証番号まで聞き出していました。
信頼を逆手に取る行動に、驚きとともに怒りを感じざるを得ません。
人は見かけによらないと、改めて痛感しますね。
事件が発覚したきっかけ
事件が発覚したのは2025年3月。
きっかけは、被害者である顧客が銀行に相談を持ちかけたことでした。
「最近、返してもらった通帳の残高が明らかにおかしい。身に覚えのない取引がある」と訴えたのです。
その一言を受けて、銀行が内部調査を実施したところ、32歳の行員による着服が発覚しました。
着服は数回ではなく、4年にわたり何度も行われていたため、銀行側もすぐには全容を把握できなかったようです。
最後は行員本人が銀行の聞き取り調査に対し、ギャンブルや借金返済に使ったと着服を認めました。
この件、顧客が気づかなければ、まだ続いていたかもしれないと考えるとゾッとしますね。
なぜ防げなかったのか?内部管理体制の問題
多くの人が「なぜこんな大規模な着服を、銀行は見抜けなかったのか?」と疑問に思ったことでしょう。
実際、このような着服が長期間発見されなかった背景には、銀行内部の管理体制の甘さが指摘されています。
定期的な口座の監査や、通帳の動きに異常がないかチェックするシステムが機能していなかった可能性が高いです。
また、行員個人への信用が強すぎて、二重チェックや交差確認といった安全網が機能していなかったとも言われています。
ふくおかフィナンシャルグループは記者会見で、今後は外部の弁護士や専門家を交えて再発防止策を講じると明言しました。
でも、こうした対策は本来、過去の事件の段階で整えておくべきだったのではという声もありますよね。
犯人が語った驚きの動機
銀行の調査によると、行員は「着服した金はギャンブルと借金の返済に使った」と説明しています。
特に、競馬やパチンコなどのギャンブルにのめり込んでいたとの情報もあり、ギャンブル依存の可能性も高いです。
一部報道では、多重債務に陥っていたとも報じられており、借金に借金を重ねて自転車操業状態だったのかもしれません。
本人が抱える経済的・心理的プレッシャーがどれほどのものだったのか、真相は明らかではありません。
だからといって犯罪が許されるわけではないと、多くの人が感じたことでしょう。
そして何より銀行員である自分がやればバレないとでも思ったのか、その油断と慢心が悲劇を招いたのかもしれませんね。
繰り返される不祥事とその背景
実はこの事件の1か月前、2024年2月にも同じ十八親和銀行で別の元行員による着服事件が発覚していました。
この元行員(58歳)は、なんと20年にわたり1人の顧客から数千万円を着服し続けていたのです。
手口は似ており、顧客との信頼関係を悪用して通帳を預かり、着服するというものでした。
同じような事件が短期間で連続して発生したことから、銀行の内部統制に対する疑念は深まっています。
「またか」という声が多く寄せられているのも無理はありません。
再発防止への本気度が、今後の信頼回復の鍵を握っていると言えるでしょう。
世間や顧客の反応・怒りの声
SNSや地域の掲示板では、今回の事件に対して多くの批判や怒りの声があがっています。
「こんな銀行に預けて大丈夫なのか」「信頼していたのに裏切られた」といったコメントが多いです。
また、「家族の貯金が狙われるんじゃないか」といった不安の声も多く見られました。
銀行側が開設した相談窓口には、すでに多数の問い合わせが殺到しているとの情報もあります。
一方で「犯人はしっかり償ってほしい」「ギャンブル依存を放置していた銀行側にも責任がある」と、制度的な問題に言及する声もありました。
地域密着型の銀行でこのような事件が続いたことで、地元の人々の不信感はしばらく払拭できないかもしれませんね。
十八親和銀行の不祥事と過去の事件との共通点
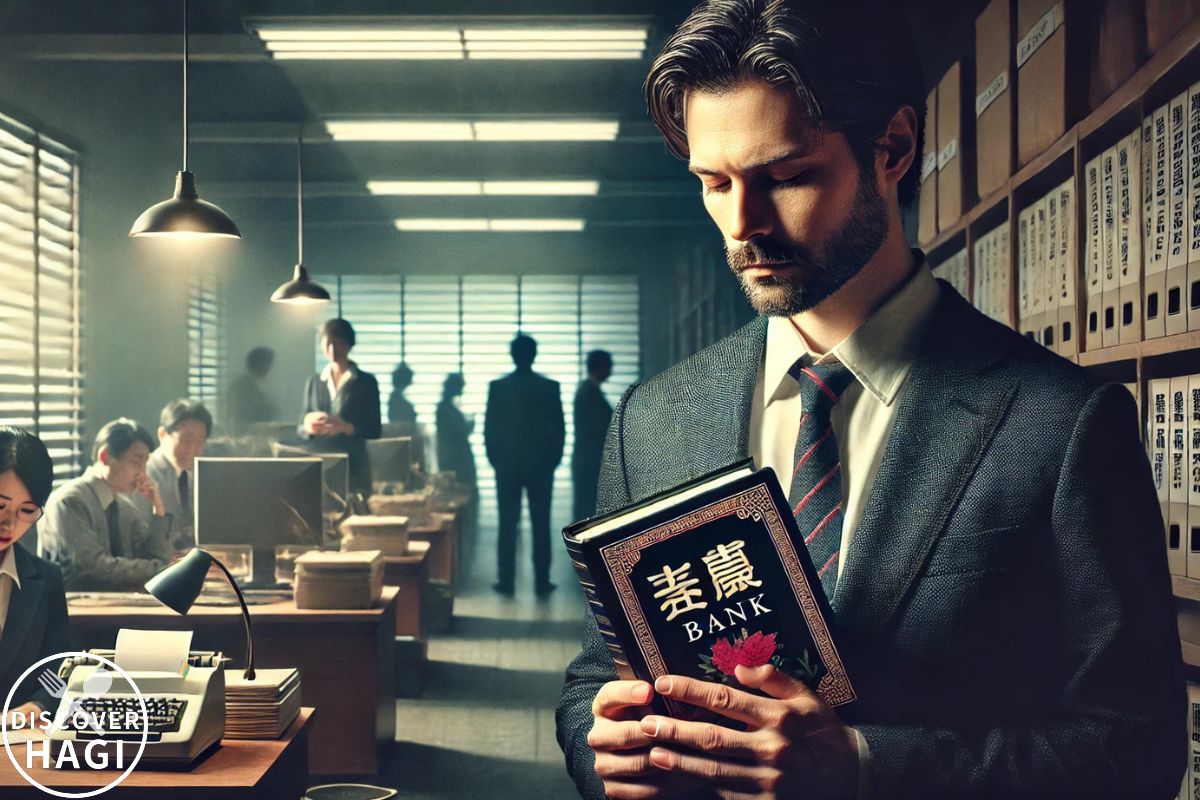
十八親和銀行の不祥事と、過去の事件との共通点について深掘りしていきます。
過去にも発覚していた着服事件
実は、今回の事件が初めてではありません。
2024年2月には、別の元行員(58歳)が顧客の資産を不正に着服していたことが発覚しました。
その金額は「数千万円」とされていますが、期間にしてなんと約20年にわたる犯行です。
この元行員も1人の顧客を対象に、定期預金の積立金を集金する際に一部を横領するという手口を繰り返していました。
「顧客との信頼関係を悪用する」「長期間にわたり発覚しない」という2つの共通パターンがすでにこの時点で表れていたのです。
この一件でも懲戒解雇と警察への通報がなされており、銀行全体に大きな衝撃が走っていました。
しかし、今回の事件が起きたことで、根本的な再発防止策が取られていなかったのではないかという声が高まっているのです。
20年にわたる犯行と元行員の異常な手口
20年間という長期にわたって犯行が続いたという点も、多くの人に衝撃を与えました。
月々少額ずつ着服することで、帳簿上の異常を出さず、あたかも自然な引き出しであるかのように見せかけていたのです。
また、顧客も高齢で、通帳の確認頻度が少なかったことも犯行を可能にした要因とされています。
この元行員もまた「生活費の補填」や「借金返済」が目的だったと供述しているようです。
ギャンブル依存の傾向も見られたようで、どちらの事件も私生活のトラブルが銀行業務に影を落としていた構図が浮き彫りになっています。
銀行という「信用」が命の職場で、個人の問題がこれほど深刻な不祥事を生む…背筋が凍る話ですよね。
再発防止策は機能していなかったのか?
2024年の不祥事の際、十八親和銀行とふくおかフィナンシャルグループは「再発防止に向けて全力で取り組む」と公言していました。
にもかかわらず、翌月に新たな不祥事が起きたという事実は、再発防止策が機能していなかったと捉えられても仕方ありません。
社員の多重債務の有無や、異常な取引パターンの検知といった管理体制の強化が実施されていなかったのではと推察されます。
また、定期的な通帳返却の義務化や、顧客とのやり取りの記録化といった「外的な目」を増やす対応も欠けていた印象です。
ふくおかフィナンシャルグループの五島社長は「外部の専門家を交えて点検を実施する」と表明しましたが、信用を取り戻すには時間がかかるでしょう。
銀行にとって最も重要な「信頼」が失われると、業務そのものが立ち行かなくなるリスクもありますよね。
十八親和銀行不祥事の犯人は誰?元行員の人物像と周辺証言

事件を起こした元行員はどんな人物だったのか?
地元関係者の証言や報道内容から、その人物像を紐解きます。
周囲が語る、犯人の性格や素行
元行員は一見、真面目で優しそうな人物に見えたと語る同僚もいます。
普段の態度は丁寧で、上司への受けも良かったようです。
しかし一方で「私生活では浪費癖があった」「パチンコ屋にいるのをよく見かけた」といった目撃情報も複数あがっています。
職場での評価と、プライベートの実態が乖離していたということですね。
また、長年一人の顧客を担当していたため、信頼されやすいポジションにいたのも事実です。
その信頼関係を悪用するというのは、人間として非常に許しがたいですよね。
ギャンブル依存と多重債務の闇
調査によると、元行員はギャンブルにのめり込み、複数の消費者金融からの借金もあったとされています。
自分の収入だけでは到底返せない額にまで膨れ上がり、最終的には顧客の預金に手を付けるようになったとのこと。
また、ギャンブルによって「一発逆転」を狙っていた節もあり、冷静な判断を完全に失っていたようです。
このような状態にまで追い込まれるまで、周囲が気づけなかったのか、職場環境の見直しも問われています。
企業として、社員のメンタルケアや債務状況を把握する仕組みの重要性が浮き彫りになりましたね。
銀行側のコメントと謝罪会見の内容
2025年3月24日、福岡市の本社で記者会見が開かれました。
登壇したのは、ふくおかフィナンシャルグループの五島久社長と、十八親和銀行の山川信彦頭取。
五島社長は「度重なる不祥事が発覚したことを厳粛に受け止め、地域の皆さまに深くお詫び申し上げます」と謝罪しました。
また、今後は外部専門家の力を借りてグループ全体のガバナンスを見直し、再発防止策を徹底すると述べました。
会見の場では、記者から「なぜ同様の事件が繰り返されたのか」という厳しい追及もあり、緊張感のある空気が流れていたそうです。
信頼を損なった以上、言葉よりも行動で示す必要がありますよね。
十八親和銀行不祥事の犯人は誰?情報まとめ

十八親和銀行不祥事の犯人は誰?情報をまとめます。
十八親和銀行の不祥事では、32歳の男性行員が約4年間にわたり顧客の通帳から約9200万円を着服していたことが明らかになりました。
その手口は、信頼を利用し暗証番号を聞き出してATMから不正に現金を引き出すというものです。
動機はギャンブルや多重債務の返済であり、本人も銀行の調査に対しそれを認めています。
さらに、2024年にも別の元行員による20年にわたる着服が発覚しており、管理体制の甘さが問題視されているのです。
親会社であるふくおかフィナンシャルグループは謝罪し、再発防止策の強化に取り組むとしていますが、信頼回復には時間がかかるでしょう。
今回の件を通じて、金融機関としての自浄能力と内部統制の強化が、ますます求められています。