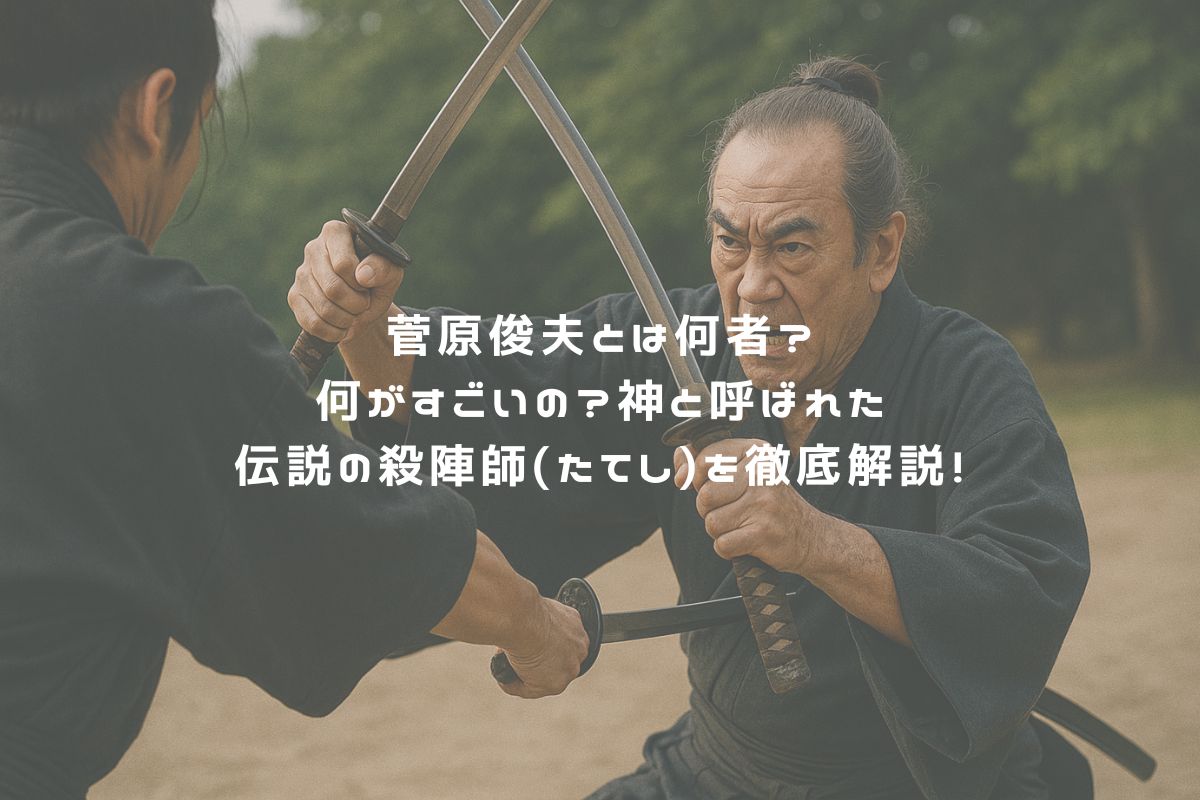\2/2(月)までスマイルSALE 開催中!/
「菅原俊夫とは?」
「菅原俊夫の何がすごいの」?
「殺陣師とは?」
そんな疑問を抱いてここにたどり着いたあなたへ。
この記事では、殺陣師という職業に人生を捧げ、日本映画や時代劇の美学を支え続けた伝説の人物、菅原俊夫さんのすごさを徹底解説します。
殺陣の奥深さ、その背後にある哲学、そして彼が後世に遺した功績まで。
ただのアクションではない、生きた表現としての殺陣の世界を知れば、もう一度時代劇を観たくなるはずです。
「なぜ名優たちは彼を信頼したのか?」
「彼の動きが芸術とまで言われる理由は?」
すべての答えを、ここに詰め込みました。
読み終えるころには、きっとあなたも菅原俊夫という存在のすごさに魅了されていることでしょう。
さあ、伝説の殺陣師が遺した物語を、一緒に辿っていきましょう。
殺陣師菅原俊夫とは?何がすごいのかを徹底解説

殺陣師菅原俊夫とは?何がすごいのかを徹底解説していきます。
菅原俊夫ってどんな人?殺陣師としての人物像
菅原俊夫ってどんな人?殺陣師としての人物像をまとめました。
| 項目 | 内容 |
| 名前 | 菅原 俊夫(すがはら としお) |
| 職業 | 殺陣師、俳優、指導者 |
| 生没 | 1940年頃生まれ(推定)〜2025年8月31日 |
| 活動期間 | 約40年以上にわたり映画・TV業界で活躍 |
| 受賞歴 | 日本アカデミー賞 協会特別賞(形道七段) |
菅原俊夫さんは、40年以上にわたって日本の時代劇界を支えてきた殺陣師であり、俳優でもありました。
殺陣師というとあまり一般には知られていない職業かもしれませんが、映画やドラマにおける立ち回りや斬られ役の指導・演出を行う職人なんです。
菅原さんはその分野において、まさに生きる伝説と称されるほどの存在でした。
何がすごいって、とにかく「動き」に魂が込められていたんですよね。
僕も実際に彼の作品を観ましたが、ただ刀を振るうだけじゃなくて、感情が宿っているんです。
セリフがなくても伝わる芝居――それが、菅原俊夫の殺陣の真骨頂だったんですよ。
なぜ殺陣師・菅原俊夫は伝説と呼ばれるの?
彼が「伝説」と呼ばれる理由は大きく3つあります。
- 数々の大御所俳優からの信頼
- 日本アカデミー賞 協会特別賞の受賞者
- 後進育成に心血を注いだ指導者としての顔
たとえば、北大路欣也さんや里見浩太朗さんといった名優たちからも厚い信頼を得ていたという証言が、取材記事からも多く見受けられました。
それって簡単なことじゃないんですよ。
大御所俳優たちは当然演技の鬼ですから、納得しないと動いてくれない。
そんな中で菅原さんは「この人に任せれば間違いない」と言わせたほど。
それってもう、本物中の本物ってことです。
東映京都撮影所で培った技術と経験
菅原俊夫さんのキャリアの出発点は、時代劇の聖地とも言える東映京都撮影所。
この場所で彼は、エキストラから始まり、スタント、斬られ役、果ては殺陣師へと昇り詰めていったんです。
「最初は後ろで倒れる役だった」とご本人も語っていたそうで、まさに叩き上げの職人。
そして、現場で数えきれないほどの立ち回りを体に叩き込んでいくうちに「こう斬れば見栄えがいい」「こう動けば物語になる」という感覚を磨いていったんですよね。
現場経験の積み重ねが、そのまま名人芸に昇華されたんだと思います。
このあたり、まさに現場が育てた巨匠って感じですね。
手がけた作品で見せた圧巻の殺陣シーンとは
彼が関わった作品は数えきれませんが、特に有名なのが以下のような時代劇。
- 水戸黄門
- 暴れん坊将軍
- 大岡越前
- 遠山の金さん
- 剣客商売
これらの作品って、一見するとどれも似たような時代劇に見えるんですが、殺陣の動きや緊張感、刀の振り方ひとつで全く違う物語になるんですよ。
たとえば「剣客商売」では、一撃必殺の「静」の美学が前面に出ていたり。
逆に「暴れん坊将軍」では、ダイナミックな「動」の派手さを重視した立ち回りが多かったりするんです。
その微細な違いを、的確に演出し続けたのが菅原さんなんですよね。
「こんなに振り幅のある殺陣ができる人って、他にいないんじゃ?」って思ったほどです。
俳優たちが信頼した「教え方」とは何だったのか?
現場で菅原さんが信頼されていた理由の一つが、その教え方のうまさ。
俳優たちが語るエピソードでは「怖そうな見た目とは裏腹に、めちゃくちゃ丁寧で優しかった」とのこと。
とくに斬られ方の指導では「リアクションの速度」「目線」「崩れ落ちる方向」など、細かく丁寧に指導したそうです。
俳優が「安心して動ける」「任せられる」と感じる殺陣師って、本当に貴重です。
ただ動きを教えるだけじゃなくて、「役になりきる感情」を教える。
それが菅原さんのすごさだったんだと思います。
「形道」との関係性は?精神性がすごすぎる理由
菅原俊夫さんは、ただの殺陣師ではありません。
彼は「形道(かたどう)」という武道の七段道士でもありました。
形道ってなに?という方のために一言で説明します。
美しい所作と心を融合した、現代に生きる武士道って感じです。
これは単なる殺陣の技術じゃなくて、どう生きるかを含んだ武道哲学なんですよね。
そこに魅かれたのが菅原さん。
戦うための技じゃなく、心と体を一致させるための道として殺陣を極めていったんです。
この精神性が、彼の殺陣をただのアクションから「芸術」にまで昇華させた理由なんでしょう。
僕自身も、菅原さんの殺陣を初めて観たとき、「これ、まるで舞台芸術じゃん」と鳥肌が立ったのを覚えています。
日本アカデミー賞協会特別賞を受賞できたワケ
最後に触れておきたいのが、彼の功績の象徴とも言える「日本アカデミー賞協会特別賞」の受賞です。
この賞は、俳優や監督ではなく裏方の功績に贈られる特別な賞。
つまり「あなたがいたから日本映画は成り立った」と言われるくらいの重みがあります。
菅原さんはその中でも、形道を通じた精神的指導や、文化の保存・伝承といった点も評価されての受賞。
まさに、技だけでなく心までも残した人だったんですね。
菅原俊夫の殺陣はなぜ評価が高いの?

菅原俊夫の殺陣はなぜ評価が高いのか?
この章ではその「理由」と「背景」に迫っていきます。
すべての所作に意味があるから
菅原俊夫さんの殺陣には、一つひとつの動きに「意味」があるんです。
ただ刀を振るだけではなく「なぜこの動きなのか」「なぜこの間合いで斬るのか」といった物語性が組み込まれているんですよ。
たとえば、敵を斬る時の踏み込み――それだけでも「覚悟」や「怒り」「哀しみ」が感じ取れるような演出がされています。
これって、振付とは違う「演出力」がないとできないこと。
まるでダンスのように流れる動きの中に、感情が宿る。
それが、菅原俊夫の型のすごさなんです。
僕も昔は「殺陣ってアクションでしょ?」くらいに思ってたんですが、彼の動きを見ると価値観が変わりますよ。
単なるアクションではなく「生き様」を見せる演出
菅原さんの殺陣には、登場人物の人生が滲み出ていると言われます。
「この人はこういう過去があって、こういう戦い方をしているんだろうな」って、セリフがなくても観客が想像できるんですよ。
たとえば、年老いた武士が戦うときは無理な動きをせず、重みのある斬り方をする。
逆に、若くて血気盛んな役は勢い重視の動きになる。
その役柄に合わせて、動きを変えるこれが本当に見事なんです。
俳優自身の表情や体格だけではなく「殺陣」でキャラクターを語らせる。
こんなことができる殺陣師って、そういないです。
見る人を惹きつける「間」と「緊張感」の極み
菅原俊夫さんの殺陣には、間の使い方のうまさがあります。
たとえば、刀を抜くまでの静寂。
一歩踏み出すまでの緊張。
その静と動のギャップが大きいほど、観る者の心を掴むんです。
たった数秒の「間」で、観客の呼吸が止まるような感覚。
まさに、日本独自の「間(ま)」という美学を体現しているんですよね。
アクション映画でよくあるガチャガチャ動き続ける殺陣とは対照的で、菅原さんの演出には「静けさの中にある鋭さ」がある。
この緊張感、クセになりますよ。
現場での即興対応力が超一流だった
実際の現場では、時間の制約もありますし、照明やカメラの位置で動きを変えなきゃいけない場面も多々あります。
そういう時、普通なら慌てるんですが、菅原さんは即座に最適な段取りを組み直すプロだったそうです。
- こっちから斬った方がカメラ映えするよ
- その位置だと被るから半歩下がろうか
なんて、現場でサッと指示して、しかもそれが完璧にハマる。
現場の信頼度、すごかったらしいですよ。
まさに、職人の域を超えて“演出家”の目線まで持っていたんですね。
名優たちが信頼した「殺陣演出の美学」
大御所俳優たちが口を揃えて言うのが「菅原さんは演じる側の気持ちがわかっていた」ということ。
どうしてかというと、彼自身が元・俳優だからなんです。
- この角度なら表情が映る
- ここで一拍置いた方が芝居が生きる
そんな見せ方まで考えた殺陣を付けてくれるから、俳優からすればやりやすいんです。
しかも、その上で「美しく」「リアルに」「感情豊かに」見えるように組んでくれる。
俳優と殺陣師、両方の視点を持っていたからこそできること。
これはもう、二刀流の神技ですよね。
自らの命を削って演出するリアリズム
晩年まで、菅原さんは現場に立ち続けていました。
それも、ただ座って「そこ斬って」なんて指示を出すのではなく、実際に動いて見せるんです。
杖をついてでも、刀を持ってでも、身体で伝えようとする姿に、若い俳優たちは感動しました。
「死ぬまで現場に立ちたい」
そんな想いを持っていたと語る関係者もいて、まさに命を削って殺陣を生きた人だったんだなと感じます。
それがまた、説得力のあるリアリズムにつながっていたんですよね。
映像越しにでも、その熱はちゃんと伝わってくるんです。
指導者としての情熱と人間味が別格だった
菅原俊夫さんは、後進の育成にも非常に熱心でした。
「殺陣という技術だけでなく、生き方を教えてくれた」と、多くの若手俳優が語っています。
たとえば「人に斬られる覚悟があるなら、自分も斬られる覚悟を持て」など、ちょっと武士道的な教えもあったそうです。
でも、頭ごなしに怒鳴ったりすることはなく、
いつも温かい目で見守ってくれる、まさに親方のような存在。
「怒られた記憶はない、でも一言一言が刺さる。」
こんな指導者、今は本当に貴重ですよね。
殺陣師として菅原俊夫は何を遺したの?後世への影響は?

菅原俊夫さんが「殺陣師」として遺したものは何か?
ただの技術者では終わらなかった彼の精神の継承に迫ります。
弟子たちに受け継がれた「形と心」
菅原俊夫さんには、多くの弟子がいました。
東映京都撮影所での演技指導をはじめ、武士道剣会や形道の稽古場でも後進を熱心に育てていたんです。
弟子たちは、単に技術を教わっただけではありません。
「斬り方」だけでなく「在り方」を学んだ。
つまり、殺陣を通じてどう人間を表現するかという深い部分を伝えられていたんですね。
彼の弟子たちは、今も時代劇や舞台の第一線で活躍中です。
そう思うと、菅原俊夫の魂は、これからもずっと受け継がれていくんだなと感じます。
映像業界が今も依存する演出メソッド
菅原さんの演出方法、つまり「カメラにどう映るか」「役者がどう動くと映えるか」は、今もなお映像業界で参考にされています。
いわゆる画になる殺陣の基礎を作った人とも言えるでしょう。
以下のような具体的メソッドが、現場では今も生きています。
- 被写体を斜めに配置して立体感を出す
- 刀の軌道を「弧」で見せることで美しさを演出
- 斬られる前の溜めで緊張感を強調
- 目線の流れを止めないよう計算された所作
現場にとっては宝のようなノウハウですね。
これが無形文化財レベルで共有されているのは、すごいことだと思いませんか?
武士道剣会や形道に与えた思想的影響
菅原俊夫さんは「形道(かたどう)」七段、そして武士道剣会の幹部でもありました。
つまり、殺陣を武道として捉える思想の持ち主だったんです。
形道とは、単に剣を振るうのではありません。
「形を通して、心を磨く」という道。
この思想を彼は殺陣に持ち込むことで、アクションを超えた精神の表現にまで高めていきました。
こうした思想は、いま武士道剣会の公式ウェブサイトや稽古資料の中にも残されています。
殺陣師=技術者ではなく、哲学者でもあったと言っていいかもしれませんね。
武士道剣会や形道に与えた思想的影響
菅原俊夫さんの殺陣を語る上で欠かせないのが「日本的な静のアクション」の確立です。
ハリウッド映画のように派手な爆発や肉弾戦があるわけではありません。
代わりに、刀を抜く瞬間の呼吸、構えの重心移動、敵との間合いそのすべてが物語になっている。
これって、日本独自の文化ですよね。
彼の殺陣は、海外の武道ファンや映画研究者にも高く評価されています。
実際に、海外で時代劇を取り上げたドキュメンタリーで「SUGAWARA Style」として紹介されたこともあるとか。
これはもう、日本が世界に誇れる静の演武芸術です。
菅原俊夫スタイルが残した殺陣師という職業の価値
菅原さんの功績でもっとも大きいのは、「殺陣師」という職業の存在意義を確立したことかもしれません。
一昔前までは「斬られ役=裏方=名もなき存在」という見方も少なくありませんでした。
でも彼が注目を浴び、評価され、日本アカデミー賞で表彰されたことにより、殺陣師という職業が「日本映画の根幹を支える存在」として認識されるようになったんです。
つまり、裏方から文化人へ。
菅原さんは、その境界線を越えたパイオニアだったのです。
映画界・演劇界の殺陣演出に今も息づく哲学
映画界・舞台界において、菅原さんの哲学は今も生きています。
たとえば舞台「刀剣乱舞」シリーズや、大河ドラマのアクションシーンなどには、見せ方に意味があるという演出哲学が色濃く残っています。
- 背中で語る殺陣
- 目線の流れが生む芝居
- 刀を振らないことで語る緊張感
これらは、まさに彼の間と心の美学から派生したもの。
彼の哲学は、弟子たちの中だけでなく、作品としても生き続けているんですね。
一人の殺陣師が築いた伝統と革新の融合
最終的に、菅原俊夫さんが遺したものは「伝統を守りながら、新たな価値を創る力」です。
昔ながらの所作、武士道の精神、形道の型それをただ保存するだけじゃなくて、現代の映像や俳優の演技と融合させた。
その結果、古臭くない、でも深みのある殺陣が生まれたんです。
これはまさに、伝統と革新のバランス感覚。
一人の殺陣師がこれを成し遂げたなんて、本当にすごいことだと思います。
伝説の殺陣師菅原俊夫とは何者?何がすごいの?まとめ

菅原俊夫さんは、40年以上にわたって日本の時代劇界を支え続けた伝説の殺陣師です。
東映京都撮影所を拠点に、数々の名作ドラマや映画で圧巻の殺陣演出を手がけました。
彼のすごさは、ただ技術が高いだけではありません。
一つひとつの動きに意味を持たせ、役の感情や生き様を殺陣に込める演出力が評価されています。
さらに「形道」や「武士道剣会」など、精神的な側面にも深く関わり、殺陣を生き方の表現として高めました。
指導者としても数多くの後進を育て、彼の哲学と技は現在も映画界や舞台芸術の中に息づいています。
殺陣師という職業の地位向上にも大きく貢献し、アカデミー賞協会特別賞を受賞したことで、その存在が広く知られるようになりました。
これからも「菅原俊夫スタイル」は語り継がれ、日本の殺陣文化を支える基盤となっていくでしょう。