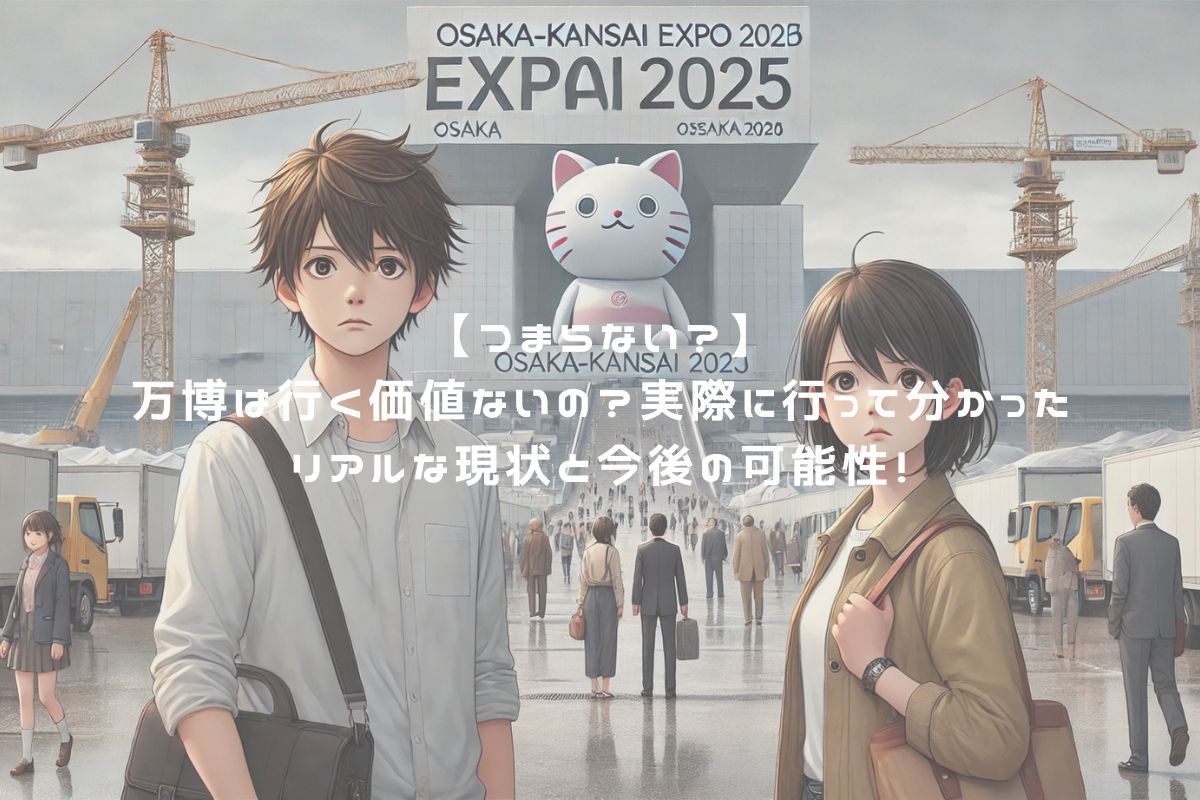\2/2(月)までスマイルSALE 開催中!/
大阪・関西万博2025がいよいよスタートしましたが「なんか行く気がしない…」「結局つまらないんじゃ?」と感じている人、実はかなり多いんです。
この記事では、実際に現地を訪れた人たちのリアルな声を元に「なぜ行く価値がないと感じるのか」「どうしてつまらないと言われてしまうのか」を深掘り。
さらに、今後面白くなっていく可能性や、期待される取組についても詳しく解説しています。
ネガティブな印象だけで判断するのはもったいないかも?
あなたが本当に行くべきか、じっくり判断できる内容になっています。
ぜひ最後までお読みいただいて、自分にとっての「価値ある万博かどうか」を見つけてくださいね。
万博行く価値ないと思う人が増えている理由とは

万博行く価値ないと思う人が増えている理由とは、近年SNSや口コミを通じて多くの声が集まってきている注目テーマです。
実際にどんな理由で「行く価値がない」と感じるのか、具体的に深掘りしていきますね。
テーマが抽象的で伝わりづらい
大阪・関西万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」です。
言葉の響きは確かに立派なんですが、いざ聞いてみると「それってどういうこと?」とピンとこない人がほとんど。
例えば「宇宙の祭典」や「世界グルメ大集合」みたいに、直感でワクワクするテーマとは違って、難しく感じる人が多いようです。
SDGsや再生医療、AIなどが中心ということで、なんとなく“カッコいい感じ”はするものの、内容のイメージがつかめないという声が多いです。
このテーマ設定が抽象的すぎて、誰の心にもグッと刺さらないのが、最初のつまずきポイントかもしれませんね。
個人的にも、「未来社会」って言われるとワクワクよりも「難しそう…」って感じちゃいました!
展示内容がまだ不明瞭すぎる
実は今の段階でも、具体的に「どんな展示があるのか」「何が体験できるのか」がまだ全貌が見えていません。
展示内容が断片的にしか公表されていないので「何が楽しいの?」「何を見に行けばいいの?」と疑問を抱く人が多いんです。
SNSをチェックしても「パビリオン情報が少ない」「どこに何があるのかわからない」という不満の声が多く見られます。
情報が少ないままチケットを買うのは、かなりハードルが高いですよね。
だからこそ「行ってもつまらなそう」と不安になってしまうのも当然です。
友だちとも話してたんですけど、何を見に行けばいいのか正直まだわからないんですよね。
アクセスが不便で疲れるとの声
会場となる夢洲(ゆめしま)は、大阪湾の人工島にあります。
現状では地下鉄中央線の延伸が予定されていますが、開通はギリギリ。
さらに、自家用車で行こうとしても道路が限られていて大渋滞の可能性も大。
現地に行くのに時間がかかって、しかも現場はまだまだ工事現場のような雰囲気。
「未来社会」とは名ばかりで「現場感」が強いという声がSNSでも多く見られます。
アクセスの不便さは、イベント参加の大きなストレスになってしまいますね。
| 項目 | 内容 |
| 開催地 | 大阪府夢洲(人工島) |
| 最寄り駅 | 地下鉄中央線(延伸予定) |
| 車でのアクセス | 道路が限られており渋滞の懸念あり |
せっかく行っても、たどり着くまでに疲れたら台無しですよね。
チケット価格が高くコスパが不明瞭
チケット価格も「行く価値ない」と感じる大きな原因のひとつです。
| チケット種類 | 価格(概算) |
| 大人前売券 | 約6,000円 |
| 当日券 | 7,500円前後 |
| 子ども料金(12歳以上) | 約4,200円 |
| 子ども料金(4歳以上) | 約1,800円 |
家族で行くと、軽く2万円以上かかることも。
そのうえ、何が体験できるのかが不透明だと「高いだけ」と思ってしまいます。
テーマパーク並みの価格に見合う楽しさがなければ「行かないほうがマシ」と感じる人が増えてしまうのも無理はありません。
正直この金額出すならUSJに行くって人が多そうです。
現地の工事感が残っていて未来感に乏しい
現在の夢洲は、工事中の雰囲気がまだまだ残っていて、写真を見ると土と鉄骨とクレーンばかり。
「未来社会」というテーマが、現地に行っても全然伝わってこないという声が多いんですよね。
SNSでも「未来感ゼロ」「ただの建設現場」といったコメントが散見されます。
これでは「未来を見に行くワクワク感」が削がれてしまいますね。
完成に近づいてからでも、この印象を覆せるかがカギです。
やっぱり見た目のワクワク感って大事だと思います!
SNSでもネガティブな感想が多数
「万博 行く価値なし」「つまらない」と検索すると、SNSでも似たような感想がたくさん出てきます。
へずまりゅう氏のレポートでは「トイレが汚い」「外国人がうるさい」などのネガティブな報告も。
また、初日に行った人の声でも「つまらない」「雨で雰囲気台無し」といった不満が続出。
ネット上で広まるがっかり体験談が、まだ行っていない人の気持ちを遠ざけてしまっている印象です。
リアルな口コミの威力は侮れません。
SNSの情報って本音が出やすいから、余計に説得力あるんですよね。
万博にそもそも魅力を感じない世代も多い
特にZ世代のような若者層にとって「万博」自体のイメージが希薄です。
1970年の大阪万博なんて教科書で見たことあるレベル。
「万博って何するの?誰が行くの?」という感覚の人がほとんど。
ディズニーやフェスには熱狂的な人でも、万博には「面白そう」と感じないのがリアルな声です。
この認知の薄さが、人気低迷の最大要因とも言えそうですね。
私もZ世代ですが、正直「万博って何する場所なの?」って感じです。
万博はつまらない?実際の声と理由を徹底調査
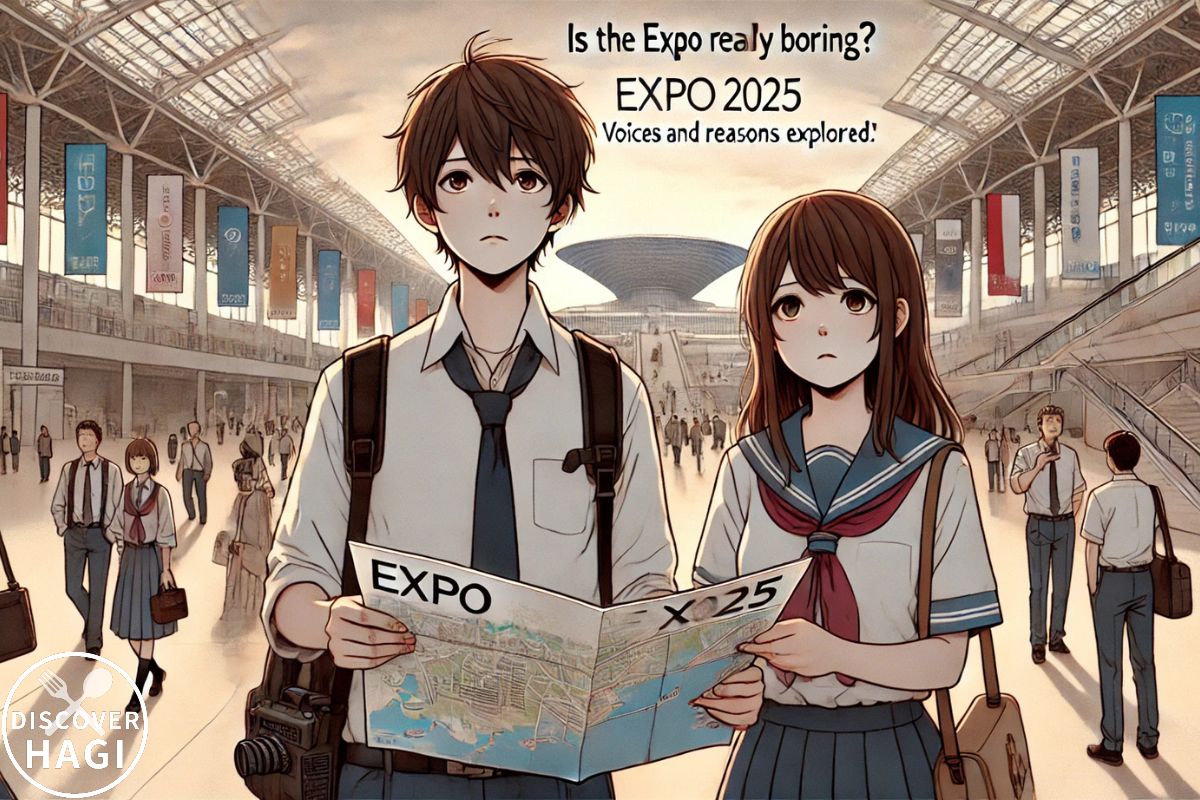
万博つまらない?実際の声と理由を徹底調査すると、驚くほどたくさんの本音が飛び交っているのです。
「どうしてそんなに不評なのか?」気になるポイントをひとつずつ解き明かしていきます!
Z世代は「万博ってなに?」という距離感
Z世代(10代〜20代後半)にとって、「万博」という言葉自体がそもそも馴染みがありません。
1970年の大阪万博はもちろん、2005年の愛・地球博すら記憶にないという人も多いんですよね。
「よくわからないもの」に対しては興味が湧きにくいのは当然のこと。
加えて、スマホ世代である彼らにとっては、「現地で見ないと体験できない」という形式そのものが時代遅れに感じるのかもしれません。
YouTubeやTikTokのように、短くてわかりやすくて面白い情報が当たり前になっている今、万博のフォーマット自体が遠い存在になっているのです。
自分の周りの若者も、「万博って何をするところなの?」って素で聞いてきます。
ひとり参加者の孤独感と退屈さ
「ひとりで万博ってつまらない?」という疑問、実はYahoo!知恵袋でもかなり多く投稿されています。
結論から言えば、ひとりで楽しめる構成やコンテンツが少ないという印象を持たれることが多いです。
たとえば、USJのようにソロでも満足感を得られる設計があるわけではなく、並ぶ・待つ・歩くの連続。
会場が広すぎて孤独感を感じやすく、展示も「感動体験」というより「学び」寄りの内容が多いため、誰かと共有したい場面が多いんです。
それゆえに「誰かと行くならまだしも、ひとりでは楽しめないかも」と不安になるのも無理はありません。
正直、私も一人で行ったら途中で帰りたくなりそうな気がします。
ミャクミャクのキャラに戸惑う声
万博の公式キャラクター「ミャクミャク」もまた、SNS上でたびたび話題に。
インパクトは強いものの「可愛いと思えない」「なんでこのキャラなの?」といった意見も多く、親しみづらさを感じる人も。
ミャクミャクのグッズやナンバープレートも登場してはいるものの、Z世代や子どもウケという点では、やや微妙な反応。
万人に愛される「ゆるキャラ」としてのポジションを確立できていない印象です。
キャラクター人気はイベントの顔となる重要な要素だけに、もっと戦略的な展開が求められそうですね。
なんだかセンスが分かる人だけが楽しめるって雰囲気があるんですよね。
パビリオンやアトラクションの乏しさ
ディズニーランドのようなエンタメ性を期待して行くと、正直がっかりするという声もあります。
万博はもともと展示と提案の場なので、アトラクションのような派手な楽しみは少なめ。
「何かが見られる」ではなく「何かを考えさせられる」という側面が強いので、行ってみても「刺激が足りない」「思ってたのと違う」と感じる人が一定数いるのも事実。
特に小さな子ども連れの家族には「子どもが楽しめる展示が少ない」「すぐ飽きてしまった」という体験談もあります。
ワクワクしたくて行ったのに、帰り道では疲労感だけが残った…なんて本音も。
やっぱり万博って知的好奇心を満たす場なんですよね。
でもそれを知らないと物足りなく感じちゃうかも。
過去の万博と比べると印象が薄い
1970年の大阪万博といえば「太陽の塔」や「月の石」など、インパクト大な展示が話題になりました。
あの頃の未来感や驚きを知っている世代にとっては、今回の万博はどうしても「地味」に見えてしまいます。
そもそも「今は何でもネットで見られる時代」において、わざわざ現地に行く必要があるのか?と感じる人も多く「記憶に残る体験」としての説得力が足りないのかもしれません。
体験の記憶が薄ければ、次につながることもない。
万博そのもののブランド力も再定義が必要になってきている時代ですね。
昔の万博って、行くだけで未来を感じられるって聞きましたもんね。
今回それがちょっとです。
SNSでは「行く価値なし」という口コミも
TikTokやX(旧Twitter)では、万博の体験レポが多数投稿されていますが、そのなかには「行く価値なし」という厳しい声も。
「トイレが初日から汚かった」「食べ物が高すぎる」「何も印象に残らなかった」といった投稿がシェアされると、それを見た人たちの興味も一気に冷めてしまいます。
SNSの発信はリアルタイムで広まりやすく、良くも悪くも「初動の印象」が重要。
その点で、オープン初日からのトラブル報告が続いたことは、万博運営にとって大きな痛手となっています。
SNSで「ガッカリ万博」ってタグ見ちゃったら、ちょっと行く気失せちゃいますよね。
現地体験者が語る「がっかりポイント」
実際に行った人の感想で多かったのが「歩く距離が長すぎる」「休憩スペースが少ない」「とにかく疲れる」といった声。
展示を見て回るだけでもかなりの距離があり、バリアフリーの整備もまだまだ不十分という印象。
また、飲食スペースも混雑していて「並ぶ→食べる→並ぶ→移動」の繰り返しに疲れ果てたという口コミも見られます。
楽しむよりもこなすような感覚になってしまうのは、イベントとしては致命的なマイナスですよね。
せっかく高いお金を払ってるのに「疲れた」って帰るのはちょっと…って思っちゃいます。
今後万博が面白くなる可能性はある?

万博が面白くなる可能性はある?という問いに対して、希望を持ちたい人も少なくないはず。
「つまらない」「行く価値ない」と言われがちな中でも、今後に期待が寄せられている動きや改善の兆しも見えてきています。
ここではこれからの万博に注目してみましょう。
大阪大学など地元の取組がカギを握る
大阪大学では、未来社会の構想や若者の参画など、ユニークな取り組みが進められています。
「未来社会の実験場」というコンセプトのもと、若い世代のアイディアを活かすイベントや、海外大学との連携なども実施。
たとえば「いのち会議」といった未来をテーマにした討論会やセッションが行われるなど、ただの展示にとどまらない参加型体験も増えてきました。
こうした学術的で創造的な取組が、本来の「万博」の意味を再認識させるキッカケにもなりそうです。
未来の社会を自分たちで作る感覚を、若い人たちが感じられる場になれば、それは行く価値につながっていくかもしれませんね。
若者が自分たちの未来を描けるイベントになれば、万博の見方も変わるかもしれないですよね!
未来社会の実験場としての可能性
「未来社会の実験場」というキャッチコピーには、正直「なんのこと?」と思った人もいるかもしれません。
でもこの言葉、よく考えてみるととても面白いポテンシャルを秘めています。
たとえば、再生医療の進展、AIによる社会サービス、次世代のエネルギーインフラ…といった“これからのあたりまえ”が、実際に体験できる場所。
それが万博会場で実現できれば、未来を五感で感じる貴重な場になりますよね。
今はまだ準備段階かもしれませんが、会期が進むにつれて展示や演出もどんどんブラッシュアップされていくことが期待されています。
未来の「当たり前」を今体験できるって、よく考えたらめちゃくちゃワクワクしませんか?
テーマ理解を深める工夫が求められる
ここまで難しすぎると言われてきたテーマですが、それをもっと分かりやすく伝える工夫があれば、逆に深い感動につながるかもしれません。
たとえば、子どもでも楽しめるようなナビゲーターコンテンツや、テーマ解説動画、AR/VRを活用した体験型展示などを強化すること。
あるいは、インフルエンサーや教育系YouTuberとコラボして“わかりやすく解説”する仕組みがあると、若年層の理解もグッと進むはず。
「難しいから行かない」から、「難しいけど、行けば分かる」に変えられるような導線を設計できれば、万博全体の評価も上がっていくでしょう。
解説付きの「おもしろ体験ガイド」みたいなのがあったら、一気にハードル下がりそうですよね!
万博は行く価値ない?つまらないと言われる情報まとめ

万博は行く価値ない?つまらないと言われる情報をまとめます。
「万博 行く価値ない」「万博 つまらない」といった声が多く見られる背景には、テーマの抽象性や展示内容の不透明さ、アクセスの悪さやチケットの高価格など、いくつかの具体的な理由があるようです。
特にZ世代には万博自体が馴染み薄く、期待値と現実のギャップが広がってしまっているのも不人気の一因。
しかし、大阪大学をはじめとする地域の主体的な取り組みや「未来社会の実験場」というコンセプトの深化によって、今後面白いと評価される可能性も十分に残されています。
少しでも興味がある人は、情報をアップデートしながら判断していくのが良さそうですね。
最新情報は»EXPO 2025公式サイトもチェックしてみてください!